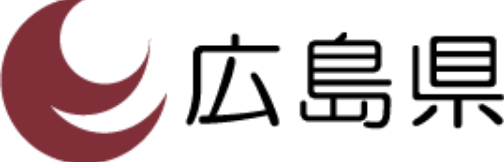研究成果・提言 ダウンロード
被爆の実相や核を巡る国際動向について学び、平和について自ら考え、発信できる人材育成の充実を図るため、広島県は、オンライン平和講座「広島から平和を考える」を開講しています。
この講座は、5つのコースで構成され、動画は全部で23本(内5つは各回の統合版)あります。以下にYouTubeのリンクを埋め込んでおります。
【第1回 広島:廃墟からのスタート】
広島を「広島」たらしめたのは、1945年8月の人類史上初の原爆投下であった。その被爆の惨禍が国内に広く認知されたのは1954年の第五福竜丸事件である。原水爆禁止運動は国内、さらには世界で急速に高まりをみせ、広島はその中心としてシンボル化していった。核兵器廃絶及び平和を考える出発点としての被爆の経験・実相を振り返るとともに、核廃絶への希求の中心的存在として広島が存在する意味を、核兵器の登場が国際政治・安全保障問題にもたらした影響や変動とともに、第二次世界大戦末期から冷戦初期の時期の動向に沿って考える。
【第2回 理想と現実:核をめぐる冷戦期・冷戦終結直後の国際政治】
冷戦期には米ソ核軍拡競争が激化し、これと並行して核兵器の拡散も進行した。他方で、そうした冷戦下の核の脅威は、米ソ核軍備管理、核不拡散体制、あるいは欧州などの核廃絶運動を生み出していく。米ソあわせて最大6万発もの核兵器を保有し対峙した冷戦が終焉を迎えたとき、世界は核軍縮の進展に期待を高めた。そして実際、米露(ソ)による大幅な核兵器削減、核廃絶決議の採択、NPTの無期限延長、CTBTの成立といった一定の成果はあった。だがその背後では、核を取り巻く国際情勢の複雑化が始まっていった。核廃絶への希求と核を巡る国際政治の現実について、冷戦からその終結直後までの動向を考える。
【第3回 複雑化する国際情勢:核をめぐる新たな脅威と現代的課題】
オバマ大統領によるプラハ演説は「核兵器のない世界」の機運を一気に高めたが、核軍縮・不拡散を巡る動向は、そうした期待を大きく裏切るものであった。国際システムの変動、安全保障環境の複雑化と軌を一にして、核の脅威は多様化し、核保有国などは核抑止の重要性を再認識し始めた。一方で、核軍縮の進展しない状況に対する強い不満は、核問題の「脇役」とみなされてきた非核兵器国や市民社会の主導によって核兵器禁止条約の策定へと収斂していく。核を巡り二分化する国際情勢のなかで、広島、日本、世界はこれから、核兵器の問題にどのように向き合っていけばよいのかを考える。
統合版
【第4回 平和への自覚:被災から復興へ】
冷戦の終結が、内戦・地域紛争、さらにはテロの頻発ももたらす中で、平和維持・構築戦後復興といった取組の重要性が高まっていった。被爆の惨劇から復興を遂げた広島は、核廃絶問題だけではなく、より広い視野で平和を考える地としての「自覚」が芽生え、広島として果たすべき「使命」を見出していく。そうした広島の活動について、特に平和構築分野での貢献や平和の担い手の育成に焦点を当てて考える。
【第5回 広島からの平和:過去・現在・未来】
平和とは何か。誰によってどのような平和があるのか。何が平和を妨げ、そのようにして平和が創られていくのか。被爆体験を出発点として広い視座で平和を考える地として広島がなすべきことについて考える。