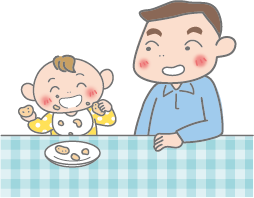本文
教えて!〇〇先生!

子育てをしていると、「これでいいのかな」と悩んだり、「どういうことだろう」と疑問に思ったりすることもたくさんありますよね。
そんな悩みや疑問にお答えし、少しでも子育てのヒントになることを願って、これまでに作成した「『遊び』は『学び』リーフレット」でご紹介してきた「教えて!〇〇先生!!」などを集めたページを作成しました。
今後も様々なテーマに応じた専門家の方にアドバイスをいただき、掲載していきたいと思います。
| テーマ | 先生からのアドバイス |
|---|---|
小学校入学に向けての心の準備~「学ぶこと」って楽しい~ |
お子さんの小学校への入学を迎えるにあたり、希望と期待に胸がふくらんでいる一方で、「小学校の勉強についていけるかな。」など学習に関する不安を感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、小学校から始まる「学習」に向けての心の準備について、小学校の先生に聞いてみました。 (小学校の先生からの話) 前回の、「小学校入学に向けての心の準備~子供の成長を共に喜ぼう~」で、「親の不安から発せられるネガティブな声掛けが、子供の不安をあおる。」というお話をしました。学習に関しては、特にこのような傾向が見られます。過去の自分自身の経験もあり、ついつい、「学習することには我慢が必要で、難しくて、辛くて、大変で・・・」と、ネガティブな言葉を並べた挙句、「・・・だから、ちゃんとがんばれ!」とか「遊んでばかりはだめだよ!」と、子供を追い詰めてしまいがちになることもあるかもしれません。子供からすれば、とうていやる気になれませんよね。 しかし、「学習=学ぶこと」は、そんなに辛いことでしょうか。もしかしたら、私たち大人も、そのように刷り込まれているだけではないでしょうか。 本来、学ぶことは、「新しい世界を知ること」であり、「できることを増やすこと」でもあり、「喜びにつながること」でもあると思います。子供は、小学校に入学する前から日々学んでいます。生活の全てが学びですし、遊びながら学んでいるのです。子供は、学ぶことが大好きで、子供にとって、「学ぶことは楽しいこと」であるはずなのです。 小学校での学習も楽しいことがたくさんありますよ。音楽科ではリズム遊び、体育科では運動遊びをします。図画工作科では、様々な材料を使って動くおもちゃやお面を作ります。そして、国語科では、新しい言葉や表現を知ることができ、算数科では、生活の中で見ていた形や時計の秘密を知ることができます。生活科では、探検したり植物を育てたりしますよ。新しく使うノートやものさしなどの文房具にもわくわくしますよね。 子供は、あらゆる体験を通して、新しいことにチャレンジしながら学んでいくのです。特に、小学校1年生の学習内容は、小学校に入学する前の遊び(経験)と非常に強くつながっています。「見たことがあるぞ。」とか「したことがあるよ。」なんてこともたくさんあります。ぜひ、小学校でも主体的に楽しみながら学べるように、小学校での学びの面白さを、お子さんとの会話の中に盛り込んでみてください。 小学校以降の学習において、最も重要なことは、「やらされる」のではなく、「面白そう」とか「もっと考えてみたい」と興味・関心をもち、主体的な姿勢で自ら取り組めるかどうかであると考えています。そして、その姿勢は、小学校に入学する前からつくられるのです。例えば、小学校で子供が困るからといって、無理矢理文字を練習させたりすることは、もしかしたら勉強嫌いを招く行為となるかもしれません。まずは、一緒にお話ししながら手紙を書いたり、絵本を読んだりして、文字を書いたり、読んだりすることに興味をもたせることから始めてみるとよいでしょう。 御自身の幼少期の学習に対するネガティブな感情は、一旦置いておいて、「学ぶことは楽しいこと」ということを、お子さんと共有すると学習への抵抗が低くなるのではないでしょうか。 |
|
小学校入学に向けての心の準備~子供の成長を共に喜ぼう~ |
お子さんの小学校への入学を迎えるにあたり、希望と期待に胸がふくらんでいる一方で、同じくらい不安が増しているという方も多いのではないでしょうか。 今回は、"小学校入学に向けての心の準備"について、小学校の先生に聞いてみました。 (小学校の先生からの話) 入学説明会などにより、準備する物は分かったものの、「自分のことが一人でできるかな。」「友達と仲良くできるかな。」「勉強についていけるかな。」と、学校生活に対するあらゆる不安は消えませんよね。 それは、子供も同じこと。いえ、大人以上に期待と不安の狭間で揺らいでいることでしょう。ただ、その気持ちをうまく言葉にして整理できないので、急に甘えてきたり、イライラしたりするような行動に移してしまうのです。 子供が不安定な入学前の時期にこそ、心に留めておきたい一つが「大人の不安や焦りを子供に伝染させない。」ということだと思います。大人が不安になればなるほど、子供への声掛けがネガティブになっていきます。「そんなことじゃ小学校に行けないよ。」「〇〇ができるようになっておかないと小学校の先生に怒られるよ。」「こんなことしてたら友達できないよ。」などのネガティブな言葉は、ますます子供の不安をあおることになりますし、学校は怖いところというすり込みにもなりかねません。また、ポジティブな言葉だとしても、「100点たくさんとれるようにがんばってね。」や「友達がたくさんできたらいいね。」などの声掛けは、過度なプレッシャーを与えることにもなります。 まず、私から皆さんに言えることは、「そんなに焦らなくても大丈夫ですよ。」ということです。一番大切なことは、子供が希望と期待をもって学校生活をスタートできることです。平仮名が書けないと本人が困るかもしれないとか、じっとできないと迷惑になるなどの心の呪縛を、大人自身が解いてください。不安に思われているほとんどのことは、小学校で十分に身に付けることができます。 子供は一人一人成長速度が違います。今、平仮名が書けなくても、様々なアイデアを出しながら遊ぶことはできているのではないでしょうか?今、じっと椅子に座れなくても、虫や植物をしっかり観察したり、友達に順番をゆずったりできているのではないでしょうか?視点を変えれば、お子さんが成長してきたことは、たくさん見えてくるはずです。そして、字を書いたり、じっと座ったりすることだけでなく、それら全てが小学校生活で生きてくるのです。 だからこそ、入学までの心の準備として、できていないことを見つけるのではなく、これまでの成長を肯定し、お子さんと一緒に喜び合ってください。けっして他者と比較することなく、小さな成長の積み重ねを褒め、「私はあなたの成長が嬉しい。」とI(アイ)メッセージをお子さんに送ってください。「今のあなたが好きだ。」と言ってあげてください。どの子供にも成長しているところはたくさんあります。子供自身が自分の成長を知った時、それは自信に変わります。周りの大人が認めてくれていることを知った時、それは安心感や勇気に変わります。おのずと、小学校への入学を前向きに捉えられるようになると思います。 それでも、心配なことがある場合は、一人で悩まず、通っている幼稚園、認定こども園、保育所等や入学する小学校、または市町教育委員会等に相談しましょう。 成長し、小学校に入学することを大人と子供が一緒に喜び合い、楽しい小学校生活の第一歩を踏み出せるようにしましょう。 |
| 一人で悩んでいませんか?(心理士) | |
| 家の中で発生しやすい「乳幼児のやけど事故」について(保育士) | |
| ”褒めて育てる”ってどういうこと?(心理士) | |
| 子供の皮膚トラブルについて(保育士) | |
| 子供の紫外線対策について(保育士) | |
| 子供を食中毒から守りましょう(保育士) | |
| 子供の熱中症について(保育士) | |
| テーマ | 先生からのアドバイスなど | 先生の御紹介 |
|---|---|---|
|
色々なものに触れたり、舐めようとするのはなぜ? |
感覚の中で最初に使われる感覚は「触覚」です。実際に、ママのお腹の中にいるとき(妊娠10週)から、触覚の学習は始まっていて、生後すぐに触れているものと見ているものが同じであるということを認識し始めます。把握反射で何かを握るときも、柔らかいものはふんわりと、硬いものはギュッと握ることができます。赤ちゃんが好奇心旺盛に何にでも触れ、舐めようとするのは、赤ちゃんにとって触れる、舐めることは、見る、聴くことよりもはるかに確かな情報が得られるからなのです。 | 七木田方美(ななきだ まさみ)先生 比治山大学短期大学部幼児教育科教授。 研究分野は、乳幼児保健学(感覚の発達・アタッチメント・障がい児保育)。保育等に関する著書、研究多数 |
|
こんな毎日で大丈夫かな? |
生活リズムを整える三つの要素は「寝る」・「食べる(飲む)」・「遊ぶ(動く)」です。朝、適切な時間にスッキリ目覚め、朝ごはんを食べ、排便し、元気に遊び、夜にはぐっすり眠ります。生活リズムは、朝起きて光を感じることでメラトニンという夜に眠たくなるホルモンのスイッチが入ります。しかし、温度も光も人間がコントロールするようになった現代社会において、大人にとっては都合が良くても、子供の体のリズムには悪い影響だらけです。赤ちゃんの誕生をきっかけに、太陽の光と温度を感じられるよう、夜はパソコンやタブレットの明かりを消して早めに眠るようにしてみましょう。毎日繰り返す睡眠は、必ず習慣となります。睡眠習慣が整った生活は、子供の幸せな未来の土台となるのです。 |
|
| 毎日おなじ遊びばかりで楽しいのかな? ~「期待通りになる」という快い安心  |
おむつが濡れて不快になると、必ずおむつを取り替えてきれいにしてくれる人がいて、お腹がすいて泣くと、必ず授乳してくれる人がいる。そこにある顔がいつも同じで、「不快」を「快」にいつも同じように導いてくれる。この「同じ」お世話の繰り返しにより乳児は「期待」を覚えます。この「期待」が「繰り返し遊び」の原点です。姿勢や手指の発達が進むと、「積木を重ねる-崩れる」「叩く-動く・音が出る」といったチャレンジタイプの繰り返し遊びが始まり、期待通りになるという喜びを、子供は満足するまで繰り返します。0歳のおむつ替えから、およそ2歳のチャレンジタイプの繰り返し遊びへの変遷は、「期待通りになる」という快い安心を、他者に与えてもらうことから自分で得るものへの変換過程。この心の自立過程に傍らにいる大人が楽しく寄り添ってあげるといいですね。 |
|
|
幼児期のお手伝いについて |
幼児期の子供たちのお手伝いは、初めは保護者の姿を真似ることの楽しさや、やってみたいという気持ちから始まるでしょう。できた程度にかかわらず、保護者から「ありがとう」の言葉が言ってもらえることで、子供たちは役に立てた喜びや、認めてもらえた嬉しさを感じます。このようにお手伝いを通して心地よさを感じることは、誰かの役に立ちたい、人と協力したいという社会性の育ちにとって大切な経験です。食事の準備や掃除などのお手伝いには、大人の繰り返しの手助けが必要なことも多いですが、ゆっくりと見守っていきたいですね。 |
上山瑠津子(うえやま るつこ)先生 福山市立大学教育学部児童教育学科准教授。 研究分野は、幼児教育学、発達心理学。子育て支援、幼児教育等に関する著書多数。 |
|
子供のイライラ、どうすればいいの?
|
子供たちはどんな時にイライラするでしょう?きっと、自分のしたいことができないときや思ったことが上手く伝えられないときですね。これは、私たち大人も同じです。イライラした時は、誰かに気持ちを受け止めてもらいたかったり、気持ちの切り替えを支えてほしかったり、時には一人にしてほしかったりしませんか?イライラが長く続くことは気持ちがいいことではありませんが、少しずつ、子供自ら自分の感情を調整していきます。乳幼児期を通して育つ子供の感情調整の発達には、周囲の大人の丁寧な関わりが大切になってきます。 | |
| こんな毎日で大丈夫かな? ~心地よい生活を創る経験  |
身体的な発達とともに、自分でできることが増えていく中で、子供たちは、心地よい生活を創る経験を積み重ねていきます。食事に合わせて箸やスプーンを使い分けることできれいに食べられたり、使ったものを片付けることで、次も気持ちよく遊べたりすることを学んでいきます。時には、どうしてこんなことにこだわるの?できないの?と思う場面もあると思いますが、スモールステップで一緒にやってみたりすることで、子供たち自身が自分の生活を自分で決めている、心地よい生活づくりの主体である経験を大切にしていきましょう。 |
|
| どうしたら「がまん」できるかな? ~認めて育つ自制心  |
自分の欲求をコントロールする力、いわゆる自制心は、幼児期から児童期にかけて発達していきます。これは、成長とともに、他者の気持ちを理解したり、自分の気持ちを表現したりする力が育っていくことが関係しています。家庭や園生活を通して、自分と他者の折り合いをつける葛藤経験は、自制心が育つ機会です。順番を守ったり、相手に譲ったり、粘り強く取り組んだりすることが、子供たちにとって心地よいと感じられる経験になることが必要です。子供たちが自制できたとき、しっかりと大人がその姿を認めていくことが大切になります。 |
|
アタッチメント(愛着)とは何ですか? |
Q.アタッチメント(愛着)とは何ですか? Q. スキンシップと愛着の違いはありますか? Q. 不安定な愛着の子供が安定した愛着を身に付けるのに遅いということはないのですか? |
梅村比丘(うめむら ともたか)先生
広島大学大学院人間社会科学研究科 准教授。 梅村先生の研究 |
|
なぜ自然との触れ合いは子供の育ちにいいの? |
自然というと、登山や海などの大自然を連想しますが、子供たちは、大人と違って、どんな小さな自然でも面白そうに遊びます。なぜ自然との触れ合いは、子供の育ちにいいのでしょうか。これにはいろいろな研究があります。その中で、私が今のところ好きな理由の一つは、自然の中で一緒に過ごす大人が清々しい気持ちになって、子供と接するのに気持ちの余裕が生まれるから、というものです。みなさんは、どうですか。 |
|
デジタル時代の子育て ~スマートフォンとの付き合い方 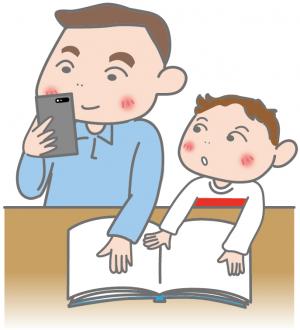 |
タブレットがコロナ禍を境に学校教育の中で一般的なものになってきました。それに向けて幼児期からスマートフォンやタブレットを積極的に使わせる家庭も増えてきているのでしょう。一方で乳児期からのスマホ依存の弊害についても耳にします。アメリカ幼児教育協会では、2歳以上の場合、将来のコンピューター使用の準備のためにスマートフォンのような双方向性のメディアに肯定的な立場をとっています。ただその使い方には注意が必要とのこと。情報の一方通行だけの視聴は避け、「子供だけで使わせない」「子供の実体験と結びつくようなものを親子で視聴する」ということを推奨しています。また子供に使う時間の制限をしておいて、自分は視聴し放題、というのも問題がありそうです。 | |
| 子供の「好き!」が 自分らしさにつながる! ~好きを見つける 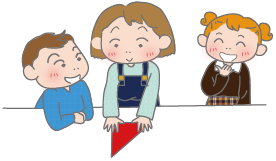 |
「好きこそ物の上手なれ」というのはよく耳にします。多くの場合、何事も上手になるのはまずは好きになることが大切だというように使われます。要するに人より秀でるためには、好きになることがその条件として必要ということでしょう。しかし、子供の育ちを見ていると、「上手になること」よりも、実は前提とされる「好きになること」の方が大切なのではないかと思うことが度々あります。子供は「好きなこと」ができ、そして逆の「嫌いなこと」もわかり、そこから自分の感情に気付いていきます。つまり、「自分らしさ」が確立されていくのです。発達心理学では、「好きになる」という感情が起こることで自己肯定感が形成され、社会性の発達の基盤になると言われています。 |
|
|
どう答える?子供の |
3歳になってやっと終わったイヤイヤ期の後には、なぜなぜ期がやってきます。話し言葉を獲得するにつれ、子供は何でも不思議に思え、「なんで?」「どうして?」と大人を質問攻めにします。大人にとっては面倒くさいかもしれませんが、この時期は、大切な発達の節目と言えるでしょう。子供の知的好奇心による「なぜなぜ期」の質問攻めは、脳が成長している証拠。知りたい気持ちが満たされることで、「もっと知りたい」「知ることって楽しい」と思うようになり、好奇心を伸ばすことにつながっていくのです。そのとき大人はすぐには答えずに「なんでだろうね?」と聞いてみてはどうでしょう。子供が自分の考えを話した時には、「知っていてすごいね」「いろいろ考えているんだね!」と褒めてください。褒められることでいろいろなことに興味を持つきっかけとなり、さらには思考力の育成や学習意欲にも結びついていくことでしょう。 |
|
| 信頼する大人との くっつきあい ~アタッチメントの大切さ 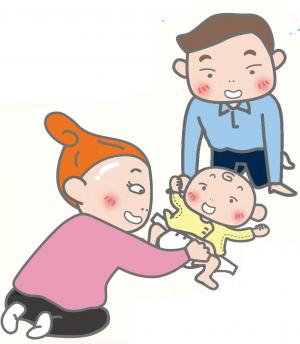 |
アタッチメントとは、心理学の世界では「愛着形成」と難しい言葉で訳されていますが、本当は「取り付けること」。親子関係で言うと「くっつきあい」のことです。信頼する大人と十分にくっついた経験が、子供の安心感という心の基地になります。安心の基地から、子供はどんどん新しい世界に挑戦していきます。失敗しても、戻っていけば、そこに「くっつきあい」をしてくれる大人がいるという安心感。この行ったり来たりが、子供の自立をつくります。大人にとっても子供との「くっつきあい」は気持ちの安定にもなりますよね。 |
|
|
食事に関する悩みは色々ありますが…
|
食事に関する悩みといえば偏食や少食、遊び食べや箸の使い方、マナーも気になるところです。子供たちが好きな歌に「どうしてお腹がへるのかな…お腹と背中がくっつくぞ」という歌があります。「おかあさんおなか空いたよ~」と、元気な声が聞こえそうです。遊んでいて気がつけばお腹がぺっこぺこ。そんな時は、ちょっと苦手な食べ物もいつの間にか口の中に入っているかもしれません。しっかり身体を動かして楽しく食べる。それは何よりのご馳走。心の栄養にもつながるのではないでしょうか。悩みもいつの間にか解決しそうですね。 | 富田雅子(とみた まさこ)先生  広島文化学園短期大学保育学科准教授。 研究分野は、幼児教育学、保育学、子育て支援。保育、子育て支援等に関する研究多数。 |
|
大人はつい手助けをしそうになりますが… |
幼児期になると全身を使ってのダイナミックな遊びが増えていきます。そして、人との関わりも増えていき、ごっこ遊びや集団遊びも好むようになります。しかし、時には意見が合わずケンカやいざこざになることも珍しくありません。目の前で子供が困っていると大人はつい手助けをしそうになりますが、そのうち子供同士で遊びにルールを作ったり、工夫をしたりして大人の関わりが必要でなくなる時期に入ります。子供同士の関わりの中で子供は様々な力を得ていきます。知恵を出し合い解決しと陽をする姿をそっと見守っていきたいものです。 |
|
| 毎日イヤイヤ・・・どうすればいいの? ~「いやー」は「こころ」が育っている証拠  |
好奇心旺盛なこの時期は、「自分でやってみよう」という行動が繰り返されます。そのことによって「できた」という満足感を得て、今度は「なんでも自分でやりたい」という欲求が芽生えます。「いやー」「自分でー」と急に泣き出したり癇癪(かんしゃく)を起こしたりすることもありますね。一見すると反抗しているようにも見えますが、実は「こころ」が育っている証拠なのです。「なぜそんなにこだわるの?」とイライラすることもあるでしょう。そんな時は、「じゃあ、どうする?」とゆったりした気持ちで寄り添ってみてはいかがでしょう。子供は、周りの人と関わることで自己をコントロールする力が育ちます。そのうち「あれはいったい何だったの?」と笑える日がきます。子供の育つ力はすごいですね。 |
|
| 「日々の暮らしの中で自然に」 ~オリジナルなふれあい遊び~ New!!  |
赤ちゃんは生まれて間もない頃から大人とふれあい、リズミカルなやり取りをすることで、社会性を発達させていくと考えられています。それは特別なことではなく、ごく自然に、日々の暮らしの中でできることです。お子さんの目を見て、落ち着いたテンポで体にふれながら、普段話す言葉を歌うように言ってみてください。たちまち楽しい、ふれあい遊びの時間になります。「ごはんだよ」「まっててね」「いちにのさん」など、オリジナルなふれあい遊びがいつでも作れます。最後にくすぐったり持ち上げたり、アレンジも楽しんでみてください。 |
本岡美保子(もとおか みほこ)先生 比治山大学現代文化学部子ども発達教育学科准教授。 研究分野は、乳児保育、保育実践、子育て支援。乳児保育、保育実践等に関する研究多数。 |
|
安心感をベースに子供の世界は広がります
|
子供は自分の意思で手を伸ばしたり体を移動させたりして、環境に働きかけることで感性を養い、感情を豊かにしていきます。そうやって、子供の世界は徐々に広がっていくのです。そのためには、子供が安心感を感じる場であることが重要です。移動している子供が振り返って大人を見た時、大人が笑顔で頷けば、子供は安心して進んでいくでしょう。子供の世界を広げるのは、こうした、大人に見守られていると実感できる安心感なのです。「まてまて」と追いかける「まてまて遊び」などの遊びを取り入れながら、子供の世界を広げてあげてください。 | |
| 絵本を介したやりとりを楽しんで ~絵本は読むもの?それとも…… 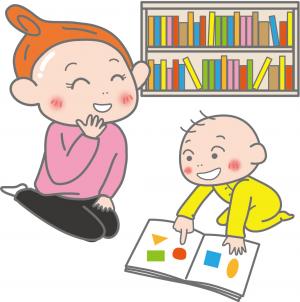 |
子供は他者とのやりとりの中で、言葉や感情、社会性を発達させていきます。やりとりのコツは、体の動きを合わせることと対乳児発話(Infant-Directed Speech)です。対乳児発話とは、大人に対するより高い声で限られた短い言葉による発話のことです。なんだか難しそう…と思われるかもしれませんが、多くの人は無意識に対乳児発話で子どもに話しかけています。絵本は、こうしたやりとりにぴったりだと思いませんか? 食べ物が出てくる絵本では、「もぐもぐ」などと言いながら食べる真似をしたりして、絵本を介したやりとりを楽しんでみてください。 |
|
| 遊びながら気持ちを通わせているんだね ~「いないいないばあ」に込められたメッセージ  |
「いないいないばあ」をすると、なぜ子供は喜ぶのでしょうか。それは、いなくなったように見える大好きなひとがちゃんとそこにいて、また現れてくれるからです。こうした経験の繰り返しによって子供は、子供にとって大好きな人との絆を、さらに強いものにしていきます。まずはお子さんと目を合わせ、それから歌うように「いないいないばあ」と言ってみてください。言葉の抑揚と拍感・リズム感によって遊びへの期待が高まり、楽しい気持ちが通じ合います。昔の人は、「いないいないばあ」が人への信頼や絆の形成に関わる遊びだということを、経験的に知っていたのでしょう。そして現代の私たちに、子供に歌いかけて共に遊ぶことが子供の育ちにとって大切なのだということを、「いないいないばあ」を通して伝えてくれているのです。 |
|
| 子供にとって心地よい感覚を… ~おやつやおもちゃの選択  |
子供は感覚を通してたくさんのことを学びます。万能なおやつやおもちゃはありませんので、子供にとって心地よい感覚を探しましょう。この時期の子供は好奇心旺盛で、なんでも触ったり、口に入れたりして感覚を確かめます。ですから、誤嚥や窒息などの命に係わる事故から子供を守る必要があります。おやつやおもちゃも4歳までは直径4センチ未満のものは避け(トイレットペーパーの芯の直径とほぼおなじです)、棒状のものは必ず大人がそばで様子を見ましょう。安全性に配慮しながら、子供の「好き」を見つけてください。 |
濱田祥子(はまだ しょうこ)先生 比治山大学現代文化学部子ども発達教育学科准教授。 研究分野は、発達心理学、保育学。保育の心理学等に関する著書、研究多数。 |
| 子供には子供の世界があるんだね ~尊重しよう!子供のイメージの世界  |
ごっこ遊びには正解がありません。また、現実世界にとらわれない自由さがあります。だからこそ、イメージの共有が難しく、思いが一致しないことがあります。そのような時、子供たちはどうしたらお互いの思いがかなうか、どうしたら楽しくなるかを考えます。そして、設定やシナリオを柔軟に変え、自分たちのごっこ遊びを作ります。ごっこ遊びでは、想像力はもちろん、創造力、計画力、他者の視点に立つ力や自己を調整する力など、多くの力が育まれます。時には、大人の仲立ちを必要とすることもあります。その際には、ごっこ遊びの自由さが育む力があることを踏まえ、大人の価値基準を押し付けず、子供のイメージの世界を尊重したいですね。 |
|
| 一人遊びは、子供の好奇心や集中力を養う時間 ~子供の一人遊びへの大人の関わり方  |
「あれ?なんだか静か・・・」振り返ると、本棚の本がバッサバサに散らばり、畳んだはずの洗濯物はグッチャグチャ!片付けのことを思うと正直ガックリですが、これこそが一人遊びの現場です。例えば、箱入りティッシュもお子さんの手にかかれば素敵な遊び道具に早変わり!一枚一枚丁寧に引っ張りながら、次を予測して取出し口を見つめています。その真剣な眼で世界を見る姿は、私たち大人にとっても学びの場です。一人遊びは、子供の好奇心や集中力を養う貴重な時間。子供の成長を思えば、片付ける手間も微笑んで受け止められそうですね。 |
橋本信子(はしもと のぶこ)先生 安田女子短期大学保育科教授。 研究分野は、幼児教育学、保育学。幼児教育、保育等に関する著書、研究多数。 |