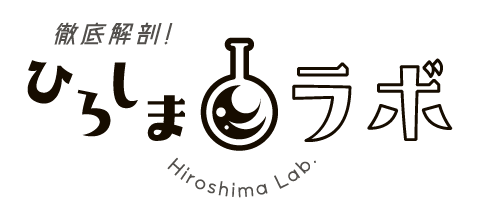「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に!?
11月5日に、ユネスコ評価機関が「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録を勧告したことが発表されました。今後ますます日本酒への注目が高まりますね!
今回は「伝統的酒造り」について解説するとともに、広島県の日本酒に関する取組をご紹介します。
目次
ユネスコ無形文化遺産とは?

ユネスコ無形文化遺産とは、ユネスコ (国際連合教育科学文化機関) が保護するべき、社会的慣習、伝統、表現、知識、技術など形のない文化のこと。2023年9月現在、日本のユネスコ無形文化遺産には22件が登録されています。
その中には、和食、歌舞伎、能楽などの日本の伝統的な文化や技術が含まれています。これらの遺産は、地域コミュニティのアイデンティティや歴史を象徴するものとして、次世代に引き継ぐべき大切な文化的財産とされています。
広島「壬生の花田植」も登録されています

「壬生の花田植」とは、広島県北広島町壬生で毎年6月の第一日曜日に行われる伝統的な田植え祭りのこと。
田の神に豊穣を祈願する行事で、牛に「馬鍬」をつけて土を砕き、囃しと歌に合わせて苗を植えます。
歴史は平安時代中期に遡り、江戸時代には「はやし田」として行われていました。牛は花鞍や造花で飾られ、太鼓や笛の音に合わせて着飾った女性が苗を植えます。
道行と呼ばれる行列や、リズムに合わせた田植え風景が見どころです。この「壬生の花田植」は西日本最大の花田植として知られており、2011年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。
「伝統的酒造り」を無形文化遺産へ提案した背景

日本酒、本格焼酎・泡盛などを作る伝統的な酒造り技術は、日本の気候風土に育まれたこうじ菌を使う独特の方法であり、日本が誇る文化です。
杜氏や蔵人たちは、こうじ菌を使いながら、日本各地の気候風土に合わせて経験に基づいた酒造りの技術を築き上げてきました。しかし、近年では生活様式の変化や高齢化により、この伝統技術を担う人々が減少しています。
この貴重な技術を次の世代に確実に継承し、さらに発展させるためには、技術の保存・活用を積極的に進める必要があるため、「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産への提案を決定した背景があります。
「伝統的酒造り」を無形文化遺産にするための取組

地域の酒造り技術とその歴史が正式に評価され、2021年12月に、「書道」とともに、初めて国の登録無形文化財に登録されました。
ワインなどの果実酒は、すでにブドウなどの原料に糖が存在するので、そのまま酵母による発酵で糖がアルコールになりますが、日本酒の場合は、こうじ菌で原料の米 (デンプン) を糖化しつつ、アルコール発酵を並行して行う「並行複発酵」を行っています。
この杜氏の技術が、他には見られない無形文化とされています。また、文化庁や保存団体が連携し、国内や海外でシンポジウムやワークショップを開催し、伝統的な酒造りの技術や文化について広く情報発信を行いました。
これにより、一般の人々にもその価値が理解されるようになり、保存・継承の必要性が広く認識されました。
広島県でも日本酒への取組を行っています
清酒酵母の育成

広島県立総合技術研究所食品工業技術センターでは広島県酒造組合と共同で、日本酒醸造の際にこうじ菌とともに重要となる「酵母」を育種しています。
中でも、2018年に誕生した「広島令和1号酵母」は、バナナやブドウを連想させる華やかでフルーティーな香りと、味のふくらみもありながら後味がキレの良い味わいになる特徴があります。
「軽快で冷酒向きの味わいになり易い」という特徴が活かされた多くの日本酒が販売されています。
酒造好適米の開発

「萌えいぶき」は、広島県で開発された夏場の高温に強い酒米です。JA全農ひろしまや広島県酒造組合等と共同で開発しました。「萌えいぶき」は、品質や収量、原料利用率が安定しています。
他の酒米と比較して収穫量が1~2割多く、米が溶けやすく豊かな味わいの酒になります。精米時に米粒が割れにくいため、大吟醸酒にも適しています。2022年1月に品種登録出願し、2023年3月には県の奨励品種として採用されました。
名称には豊かな大地の力強さと、造り手の夢や希望、熱い思いが込められています。
広島県産日本酒のブランド化

2023年5月に広島で開催されたG7サミットでは、地元の食材を使った料理が振る舞われ、広島が誇る食文化に注目が集まりました。
このチャンスを活かし、湯﨑広島県知事は2023年10月14日から17日にかけてフランスを訪れ、「かき」と「日本酒」のトップセールスを実施。ディジョンでのワイン即売会「Salon des vin Dijon」では広島の日本酒をPRし、パリのミシュラン一つ星レストランでは県産かきとのペアリングイベントを開催しました。
特に日本酒とかきの相性の良さがフランスの参加者から高評価!こうした海外での活動により、広島の日本酒と食材の認知度向上と販路拡大が期待されます。
広島県産酒の需要拡大を目指すこれらの取組が、「伝統的酒造り」を、次の世代に確実に継承し、さらに発展させることにつながっていきそうですね。
「伝統的酒造り」に、今後さらに注目が集まりそう!

「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録される見込みとなったことで、今後、酒造りに注目が集まることは必至!
広島県には、東広島市「西条」という、兵庫県の灘、京都府の伏見とともに日本三大酒どころとして有名な地域があり、現在も伝統的な酒造りが続いています。
また、毎年、10月の3連休の土・日曜の2日間にわたって、JR西条駅周辺で「酒まつり」が行われています。
興味を持たれた方は、酒蔵巡りや、来年の酒まつりに行ってみてはいかがでしょう。