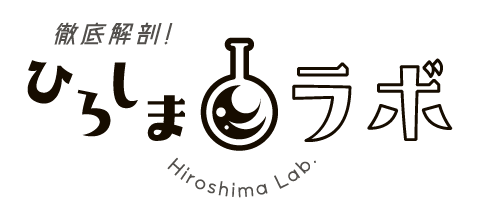広島県が生産量日本一!「慈姑」ってどんな野菜?
広島県で日本一のもの、と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか?牡蠣、レモン、お好み焼…などなど。最初に「慈姑」を思い浮かべる方は少ないのではないでしょうか。
「慈姑」は「くわい」と読みます。それなら知ってる!という方や、おせち料理で食べた、という方もいらっしゃるかもしれませんね。くわいは、実から立派な芽が伸びるその形から、「食べると芽が出る」縁起のよい食べ物とされています。このくわい、広島県福山市が生産量日本一。なんと全国シェアは約7割もあるんです。ご存知でしたか?
※農林水産省「平成28年地域特産野菜生産状況調査」
今回は、くわいがどんな野菜なのか、また、くわいと旬の牡蠣を使ったレシピもご紹介します。
青色が鮮やか!美しい外観の「青くわい」

くわいはオモダカ科の水生多年草で、中国が原産です。アジアやヨーロッパ、アメリカにかけて広く自生していますが、食べる習慣があるのは日本と中国だけだそうです。土を掘り起こす鍬 (くわ) のような形をした葉の下に、芋のような実がなることから「くわいも」と呼ばれ、それがなまって「くわい」になったとも言われています。
くわいには、青くわい、白くわい、吹田くわいの3種類あり、日本では主に青くわいが栽培されています。おせち料理に使われているのも主に青くわいです。
福山市で栽培されているのは「青くわい」で、形はコロンとした円球形。つやのある表面の青みの鮮やかな藍色はとても綺麗なんです。その美しい青藍色から「田んぼのサファイア」とも呼ばれているそうですよ。
なぜ福山で栽培されてきたの?
福山は瀬戸内の温暖な気候で日照量が多く、もともと青くわいの生育に適していました。福山市のくわい栽培は、現在の福山市千田町の沼地に自生していたものを、明治35年頃、福山城周辺の肥沃な堀に持ってきたのが始まりとされています。また、江戸時代、福山藩が新田開発をする際に、芦田川の水を送るため網目状の用水路を増設したことから、多量の水を確保することができる環境にあったことも、くわい栽培が盛んになった一因のようです。

福山市で栽培されたくわいは、「福山のくわい」として2020年に地理的表示 (GI) 保護制度にも登録されています。高い品質を維持し、等級・階級・サイズ毎に厳しく選別された「福山のくわい」は、高い評価を受けています。
くわいと広島かきの日本一レシピ
くわいはおせち料理の食材としての需要が高いため、出荷時期も11月~12月に集中しています。青くわいはタンパク質やカリウムが豊富。ほっこりとした食感で、食べるとほろ苦さのなかに甘味が残るのが特徴です。
おせち料理に入っているくわいは煮物が多いため、ここでは過去の県民だよりに掲載したレシピの中から、くわいと同じく生産量日本一の牡蠣をつかったおススメレシピをご紹介します。くわいと牡蠣が手に入ったらぜひ作ってみてください。
広島かきとくわいの炊き込みご飯

材料
4人分
| 生かき (加熱用) | 1パック (約200g) |
|---|---|
| 塩 | 小さじ1 |
| お米 | 2合 |
| くわい | 6個 (Mサイズ) |
| 人参 | 30g |
| [生かきの下味用調味料] | |
| 昆布出汁 | 約350ml |
| 酒 | 大さじ2 |
| みりん | 小さじ2 |
| 醤油 | 小さじ2 |
作り方
- 生かきに塩を振り、優しくもみ洗いし、水を張ったボウルの中で洗う。生かきの水分をしっかり拭き取る。
- くわいの皮を剥き、縦半分に切る。
- 鍋に [生かきの下味用調味料] を入れ中火にかけ、沸騰したら生かきとくわいを入れて約2分下茹でする。灰汁を取り除いた後、かきとくわい、調味料に分けておく。
- 洗ったお米を炊飯器に入れ、(3)の調味料を炊飯器の目盛りに合わせて入れる。くわいと細く切った人参を加え、通常モードで炊き上げる。
- 炊き上がったら(3)のかきを入れ、約5分蒸らした後、下から大きく混ぜれば出来上がり。