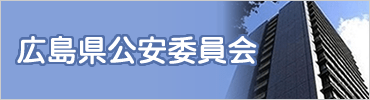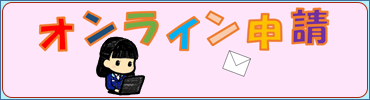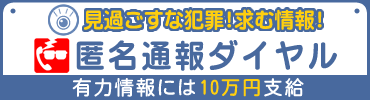令和7年度 第1回 廿日市警察署協議会
開催日時
令和7年7月2日(水曜日)午後3時30分から午後5時15分までの間
開催場所
廿日市警察署
出席者
協議会 会長以下7名
警察署 署長以下9名
協議会概要
感謝状贈呈
当署管内情勢の説明
- 管内の治安情勢
- 管内の交通事故発生状況、速度取締り指針
質疑・要望・協議等
県の防犯カメラの設置のガイドラインについて(生活安全課長)
防犯カメラは犯罪抑止力の高い有用なもので商業施設や金融機関、駐車場などで普及し、また、市町や町内会などが公共空間に防犯カメラを設置するケースが増えています。
一方で、多様な主体が防犯カメラを設置することによって、知らないうちに自分の姿を撮影されることに不安を感じる方もいます。
県では、そうしたプライバシーの侵害に対する不安を解消し、防犯カメラの適切かつ効果的な活用を推進するためガイドラインを策定しています。
また、廿日市市では、地域において犯罪の発生の抑止、市民の安全・安心の確保および犯罪が発生した場合の早期解決に資することを目的として、町内会や自治会などが屋外の特定の場所へ防犯カメラを設置することについて、その設置費用を一部補助をする制度があります。
地域の特性にあった免許証の自主返納対策について(交通課長)
廿日市市には、高齢ドライバーによる交通事故の防止を目的とした、満65歳以上の廿日市市民への「高齢者運転免許自主返納支援制度」があります。
廿日市警察署管内での免許返納者は、年々増加しています。
公共交通機関網の新設・変更等について、廿日市市の公共交通機関に関する協議会がありますので、同協議会での議題として提案していきたいと思います。
廿日市警察署管内では、高齢者の交通事故の割合が高く、事故当事者が重症化する傾向にあります。
人間の身体機能は、年齢を重ねると徐々に衰え、遠視が始まってきた方々の中には、「夜間の運転が以前に比べ苦手になってきた。」「車両の後退が苦手になってきた。」とおっしゃる方が多いです。
このような症状を感じ始めたら、
- 運転を控える
- 免許返納を考える
きっかけになると思います。
免許返納については、いろいろと事情があると思いますが、警察としては高齢者の方本人や事故の相手方など、悲惨な結果に繋がらないように、高齢者対象の安全教室や家族の協力を得て免許返納を推進しております。
また、廿日市市などと連携を密にして、免許返納がしやすい環境作りを行っていきたいと思っております。
いたずら電話対策について(生活安全課長)
いたずら電話があった場合、警察に電話して相談をしていただければ、どのような対処ができるか検討します。
自主防犯の方法としては、
- 留守番電話機を録音状態にし、相手の声を確認した上で応答する
- 留守番電話機で全てのメッセージを受け取り、用事のある人にはこちらから電話をかけ直す
- 「ナンバーディスプレイ」「迷惑電話おことわりサービス」などの各種電話会社等が提供するサービスを利用する
があります。
無言電話・いたずら電話は、他人に不安や迷惑をかける行為として、偽計業務妨害罪に抵触する可能性があります。
他罪については、電話の内容や被害の程度、電話の相手との関係性など、総合的に判断することになります。
いたずら電話がかかってきた際には、事件化に向けて、記録化(電話番号、着信時間、終了時間、内容)や録音をしてください。
青色防犯パトロールについて(生活安全課長)
青色防犯パトロールが始まった経緯ですが、広島県では平成15年から全国に先駆けて「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動が開始され、「地域の安全は地域で守る」という意識のもと、多くのボランティア団体や防犯パトロール隊が結成され、平成16年12月1日から、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は、青色回転灯を装着した自動車による防犯パトロールを行うことができるようになりました。
青色防犯パトロールの目的は、
- 犯罪・事故・災害の被害を未然に防ぐ
- 地域の皆さんが安全に対する関心を高める
- パトロールに参加することで、地域の連帯感を醸成する
- 地域の犯罪抑止機能を向上させる
です。
青色防犯パトロールの実施方法として、一般の自動車に回転灯等を装備することは法令で禁止されていますが、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は自動車への青色回転灯等の装備することができます。
現在、廿日市警察署管内では、7団体約900名の方が実施しており、青色防犯パトカーの台数は約60台あります。
ストーカー事件の未然防止対策等について(生活安全課長)
県下において、昨年1年間で600件近くのストーカーの相談を受理しています。
ストーカーの特徴としては、最初は小さな嫌がらせから始まり、行為が段々とエスカレートしていき、最悪の場合は殺人事件にまで発展することもあります。
ストーカーになるきっかけとして、1番多いのは「元恋人関係」、その他に「知人・友人」「勤務先の同僚や職場関係者」があります。
別れ話のもつれが原因となってストーカー事案に発展するケースがありますが、ストーカーの行為者が元恋人や友人、知人ということもあり、警察への相談をためらい、被害が潜在化してしまうことがあります。
警察は、相手に対して検挙や警告等の対応をとることができます。
その他、避難等の支援、被害防止のための資機材の貸し出しや、自宅等の周辺のパトロールを行います。
ストーカーによる被害を防止するために、できるだけ早く警察へ相談してください。
身に危険を感じるような緊急の場合は、遠慮なく110番通報をお願いします。
高速道路での逆走対策等について(交通課長)
いわゆる逆走が原因による人傷事故については、令和6年中では広島県内で1件の発生があり、令和7年中(5月末現在)では2件の発生がありますが、当署管内での発生はありません。
全国的には、高速道路などでの逆走は、近年でも多数発生しており、運転手の大半が65歳以上の高齢者であるのが現状です。
もし、高速道路で逆走してしまった場合などですが、気付いた時点で、向きを変えようとはせずに、直ぐに路肩や非常駐車帯に寄せて停車し、ハザードランプを点灯させてください。
そして、車から降りて、ガードレールの外側など安全な場所に避難して110番通報をしてください。
次に逆走を防ぐ対策についてですが、
- 降りる予定であったインターチェンジを通り過ぎてしまったとしても、絶対にバックやUターンをすることなく、必ず次のインターチェンジで降りること
- 高速道路などでは、インターチェンジや合流部などの要所には進入禁止標識や逆走の注意喚起をする標識などが必ずあるので、その標識などを良く見て運転すること
を守っていただくことが重要です。
また、警察としての逆走対策は、高速道路に限らず一般道も含めて
- 道路管理者と連携して道路整備(注意喚起標識の設置等)を行う
- 交通安全講習や広報媒体等を利用しての教育・広報活動を行う
- 高齢運転者に対する運転免許の返納を推進する
等の対策を継続して、逆走による悲惨な交通事故の防止に努めてまいります。
その他
協議会の会員による廿日市警察署の施設見学を実施しました。