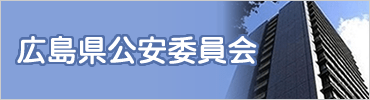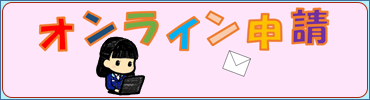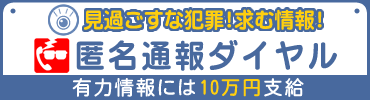安全で楽しい登山のために(冬期)
山岳遭難対策の必要性
広島県には、瀬戸内海から中国山地まで、さまざまな風景が楽しめる魅力的な山がたくさんあり、県内外から多くの登山者が訪れています。
それらの山々は、いずれも標高が1,500メートル以下で、比較的簡単に登ることができると思われがちですが、実際は、道迷いや滑落により遭難したり、尊い命が失われるような山岳遭難も発生しています。
年間山岳遭難発生件数(件数)
| 区 分 |
令和4年 |
令和5年 | 令和6年 |
増減 |
|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 29 | 34 |
33 |
-1 |
年間山岳遭難者数(人数)
| 区 分 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
増減 |
|---|---|---|---|---|
| 死者 |
2 |
4 | 4 | ±0 |
| 行方不明者 |
0 |
0 | 0 | ±0 |
| 負傷者 | 15 | 7 | 14 | +7 |
| 無事救出 | 22 | 34 | 19 | -15 |
| 合 計 | 39 | 45 | 37 | -8 |
令和6年12月~令和7年2月(冬期)は、4件(5人)の山岳遭難が発生し、1人が軽傷、4人は無事救出されています。
冬山登山の遭難事故防止
広島県の雪山は、西方「芸北エリア」、東方「比婆エリア」に分かれ、冬期は両エリアとも最高気温が−0℃以下となり、山中では1mを超える積雪を観測する時もあります。
遭難を防止するためには、体力・技術・経験に応じて登山する山を選び、現地の気象状況や登山ルートなどをよく確認して入山することが大切です。
少しでも不安を感じたら、無理な行動は避けて「引き返す勇気」を持つことが必要です。
そこで、冬山登山をされる際は、次の点に留意してください。
無理のない登山計画を立てましょう
冬山は天候が変わりやすく、気温の低下で体力を激しく消耗することもあります。
不測の事態が発生するケースも多いため、体力・技術・経験・体調などに見合った山を選択し、ゆとりのある行程で無理のない登山計画を立てましょう。
体力に自信がない参加者、経験の浅い参加者を基準に行程を決めるなど、安全を第一に計画を立てましょう。
事前に十分確認し、山小屋の休業や登山道の閉鎖を知った場合は、無理をせず、登山する山の変更や計画の中止・延期を検討しましょう。
登山計画を家族や職場にも知らせておきましょう。
登山届(登山計画書)を作成し、事前に登山する山岳を管轄する警察署や広島県警察本部地域課に提出しておくことで、万が一の際、捜索活動をスムーズに行うことができます。
十分な装備品、服装、食料等を整えましょう
装備品や携行品を十分点検し、取扱い方法をよく確認しておきましょう。
服装は、冬山の気候に順応した、防水性、防寒性、保温性に優れたものを着用しましょう。
冬山では足元が滑りやすくなることもあり、転落・滑落防止や疲労軽減のため、冬山登山に適した靴を使用しましょう。
また、安全に登山するため、ストック(トレッキングポール)やヘルメットなどを用意しましょう。
ラジオ・携帯電話機(無線機)は、登山の必需品です。
万が一遭難した際に救助を求めるための連絡用通信機を携行しましょう。
GPS機能付きの携帯電話等は、救助要請手段として有効ですが、山中では圏外となることも多く、バッテリーの消耗が激しいため、常に充電状態を確認し、予備電源(電池、モバイルバッテリー等)を用意しましょう。
冬山登山では、自分でも気づかない間に脱水症状を発症することもあるため、必ず飲料水を携行しましょう。
事前に自動販売機の位置や給水ポイント等を確認し、万が一に備え、食料等も十分準備しておきましよう。
現地の気象や山の状況を把握しましょう
入山前に、現地の気象状況(降雪)や、登山ルートの状態(積雪)などについて情報を入手し、場合によっては計画の変更や中止を検討してください。
降雪があると、視界不良で道に迷ったり、登山道を見失うなどして事故が発生する可能性が高くなります。
積雪も同様に、迂回を余儀なくされ道に迷ったり、足元が滑りやすくなるなどして転落や滑落の原因となることがあります。
天候以外にも、ガスや霧などにも注意が必要です。
登山ルートの閉鎖・変更なども、道迷いや転落・滑落の原因となることがあります。
必ず事前に気象状況や危険箇所、登山ルートの状態を確認しましょう。
トラブル発生時に途中から下山できるルート(エスケープルート、迂回ルート)等を把握し、登山中は常に最新の気象情報の把握に努めてください。
複数人で登山しましょう
単独登山は大変危険です。
動けなくなったり携帯電話が圏外の場合など、自分で救助要請ができないこともあります。
転落や滑落などにより登山道から外れてしまった場合も、他の登山者に気づいてもらうことができません。
可能な限り、経験豊富な信頼できるリーダーを中心とした、複数人でパーティを組んで登山しましょう。
経験豊富な方でも不測の事態が起きることもあるため、可能な限り複数人での登山を心がけてください。
「複数人で、より安全で楽しい登山」をしましょう。
道迷い防止
地図、コンパス、登山アプリ、地図アプリなどを有効に活用して、常に自分の位置を確認するよう心がけましょう。
地図の見方やコンパスの使用方法を事前に習得しておきましょう。
登山アプリと紙の地図を併用することで、より正確な位置を把握することができます。
アプリを現地でインストールすると、バッテリーの消耗や通信制限の原因となりますので、事前にインストールしておきしましょう。
「道に迷ったかも」と思ったら、今歩いてきた道(トレース)を辿り、正規の登山道まで引き返すなど、的確に状況を把握しましょう。
自分の位置がわからなくなった場合は、闇雲に移動せず、他の登山者に助けを求めたり、通報して救助を要請しましょう。
闇雲に移動すると、さらに複雑な場所に迷い込んだり、滑落や転落をするおそれがあるため、冷静さを保ち、落ち着いて行動しましょう。
滑落・転落防止
滑りにくい登山靴を使用しましょう。
ストック(トレッキングポール)やピッケルなどを携行し、有効に活用しましょう。
特に、雪山では、冬用の登山靴やアイゼンなど専用の装備品が必要とされています。
天候や積雪に応じた装備を使用することで、滑落や転落事故を防止しましょう。
悪天候などにより視界不良となった場合は、滑落や転落を防止するため、闇雲に移動しないようにしましょう。
的確な状況判断
登山中の視界不良や体調不良時には、道に迷ったり、転落・滑落などの事故に遭うおそれが高くなるります。
状況を的確に判断して、早めに登山を中止しましょう。
視界不良となった場合や体調不良時には,無理をして移動せず,通報するなどして、すぐに助けを求めましょう。
少しでも不安を感じたときこそ、早めに状況判断をしましょう。
天候や健康状態に少しでも不安な要素があれば、登山を別の日に延期しましょう。
熊等動物への対策
広島県の山域には、熊、猪、鹿、猿などの野生動物が生息しています。
熊は、冬眠中はずっと眠っているイメージがありますが、冬眠中であっても場所を移動したり、餌を求めて活動することがあると言われており、冬期間中でも注意が必要です。
登山をする際は、熊鈴や熊スプレーを携行するなどの対策をしましょう。
可能な限り複数人で行動し、音を立てるなどして、熊に出会わないようにしましょう。
登山届(登山計画書)の作成
登山届(登山計画書)は、登山者の氏名、年齢、連絡先、緊急連絡先、目的山域・山名、登山の予定、ルート、携行する食料の量、装備品などを記載します。
山岳遭難や行方不明時に捜索の手がかりになるだけでなく、他の入山者からの目撃情報など、捜索に有効な情報を得るための助けになります。
作成した登山届(登山計画書)の写しを、家族や職場など身近な人に渡しておきましょう。
登山届(登山計画書)は、特に決められた様式はありません。
下記様式は、公益社団法人日本山岳協会のホームページに掲載されている参考書式例です。
必要であれば、プリントアウトまたは修正してお使いください。
登山届(登山計画書)の提出
登山届(登山計画書)を作成したら、広島県警察本部地域部地域課指導係又は登山する山を管轄する警察署地域課に、郵送またはFax送信等で提出してください。
県外の山に登山する場合は、お手数ですが、登山する山を管轄する警察本部地域課または警察署地域課にご確認ください。
- 広島県警察本部地域部地域課指導係
- 登山する山を管轄する警察署地域課(警察署地域課に提出する場合は、登山する山の地域を確認し、事前に連絡してください)
登山アプリで登山届を作成する
登山届(登山計画書)は、登山アプリでも作成することができます。
広島県警察は、令和5年11月6日に、
- 山岳安全対策ネットワーク協議会(登山届受理システム「コンパス」)
- 株式会社ヤマップ(YAMAP)
と協定を締結しました。
山岳遭難等の事故が発生した場合、協定に基づいて、アプリ上に登録された情報を確認し、捜索や救助活動に活用することとしています。
オトモポリスの活用(現在地送信機能)
☝画面をクリックしてください。
外部リンク
内閣官房及び内閣府オフィシャルサイト 政府インターネットテレビ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)