つつが虫病について
,
つつが虫病はダニの仲間のツツガムシの幼虫によって媒介される細菌の仲間 つつが虫病リケッチア Orientia tsutsugamushi によって起こる感染症です。野外でリケッチアを保有するツツガムシの幼虫に「吸着」されることで感染します。日本では古くから東北・北陸地方で夏季に発生する風土病として知られていましたが、戦後になってその他の地域でも確認されるようになり、北海道など一部の地域を除いてほぼ全国で発生が見られるようになりました。
同じようにダニの仲間のマダニ類によって起こる日本紅斑熱とは臨床症状がよく似ているため、確定診断には抗体検査や遺伝子検査が必要です。
疫学
古くから知られていたいわゆる「古典的つつが虫病」は主にアカツツガムシによって媒介され、東北・北陸地方を中心に夏季に患者が多発していました。戦後になって患者が増加したいわゆる「新型つつが虫病」は、タテツツガムシやフトゲツツガムシの幼虫(図1)によって媒介され、幼虫が活動する春と秋~初冬にかけて患者の発生がみられます。広島県で確認されているのは、「新型つつが虫病」の方です。
広島県内の患者発生は春と秋~初冬に集中しており、患者の推定感染地域は広範囲です(図2)。患者からはタテツツガムシに媒介されるKawasaki型、フトゲツツガムシに媒介されるKarp型のつつが虫病リケッチアが検出されています。Kawasaki型の患者は県西部の太田川中流域を中心に県の西側で、Karp型はほぼ全域で確認されています。患者の感染時の行動としては田畑での農作業や山林作業、レジャーなどが多く、患者は中・高年に多く発生しています。
 図1 ツツガムシの幼虫 |
臨床症状
10~14日の潜伏期間を経て(日本紅斑熱より長い)、頭痛や倦怠感、寒気などのかぜ様症状とともに急激に発熱(38~40度の弛張熱、悪寒戦慄を伴う)した後、顔面や体幹部に米粒大や小豆大の紅斑が出現します。この紅斑に痛みやかゆみはありません。体中を注意深くさがすと皮膚にかさぶたを伴った特徴的なツツガムシの刺し口(図3)が見つかります(刺し口は臀部、外陰部、大腿部や腹部など、皮膚の柔らかい隠れた部分にある場合が多い)。発熱、刺し口、発疹はつつが虫病の三大特徴です(日本紅斑熱も同様)。
検査所見では、CRP の上昇、肝酵素(AST、ALT)の上昇、白血球や血小板の減少などがみられます。
つつが虫病は適切な抗菌薬を用いた治療を行わないとDIC(播種性血管内凝固症候群)を起こすなど重症化し、まれに死亡することもあるため、早期の診断と投薬が重要です。
 図3 ツツガムシの刺し口 と発疹 |
病原診断
患者の確定診断は、ペア血清による抗体上昇の確認など血清診断が一般的です。また、PCR法により急性期の患者血液や刺し口の痂皮からリケッチア遺伝子を検出することも行われています。
県保健環境センターでは5種類のリケッチア抗原(Kato、 Karp、 Gilliam、Kawasaki、Kuroki株)を使用した間接蛍光抗体法(図4)による血清抗体価の測定や、PCR法による遺伝子検査を実施しています。
なお広島県では、つつが虫病と臨床症状がよく似た日本紅斑熱の患者が発生しているため、日本紅斑熱についての検査も併せて実施しています。
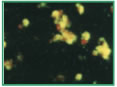 |
| 図4 間接蛍光抗体法による 抗体の検出 |
医療機関の方へ:検査については管轄の県保健所へ問い合わせてください。
つつが虫病・日本紅斑熱・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)患者調査票 (PDFファイル)(166KB)
治療
つつが虫病の治療には、早期につつが虫病の可能性を疑って適切な抗菌薬を投与することが極めて重要です。治療にはテトラサイクリン系の抗菌薬が最も有効で、βラクタム系の抗菌薬は効きません。
感染予防
感染予防にはツツガムシの吸着を防ぐことが重要です。田畑での農作業や山野での作業をする際には、以下のような対策をとります。
- 長袖、長ズボンなどを着用して皮膚の露出を避け、すそを入れ込んでダニの付着や服の中に入ってくるのを防ぐ。長靴を履くのもよい
- 肌が出る部分には防虫スプレーを噴霧する(効果は限定的)
- 作業後は体や服をはたき、帰宅後はすぐに入浴して身体をよく洗う。また、衣服は放置しないですぐに洗濯する
なお、野外での作業などの数日~10日前後で発熱・発疹などが認められた場合には、できるだけ早い時期に医療機関を受診して、つつが虫病あるいは日本紅斑熱に感染した可能性があることを告げ、検査・治療を受けてください。
届出基準
つつが虫病は感染症法の分類で4類感染症全数把握疾患となっており、診断した医師は直ちに最寄の保健所に届け出る必要があります。報告の基準は臨床症状や所見からつつが虫病が疑われ、かつ以下のいずれかの方法により病原体診断や血清学的診断がなされたものとなっています。
- つつが虫病リケッチアの分離(血液などからの病原体の分離)
- つつが虫病リケッチア遺伝子の検出(PCR法による検出など)
- 抗体の検出(間接蛍光抗体法や間接免疫ペルオキダーゼ法によりペア血清でIgG抗体価が4倍以上上昇するか、IgM抗体の上昇が確認されるなど)
啓発用資料
野外で活動する時にはダニにご用心! -ダニからうつる病気「つつが虫病」と「日本紅斑熱」- (PDF:239KB)
広島県のダニ類媒介感染症 ~つつが虫病,日本紅斑熱,重症熱性血小板減少症候群(SFTS)~ (PDFファイル)(1.42MB)
参考資料
- 広島県におけるつつが虫病患者発生状況と検査対応状況,IASR(病原微生物検出情報),Vol. 43(2022),p181-182.
- 昭和62年広島県環境保健部監修「つつが虫病の診断にあたって」
- 積山 幸枝ら (1991):広島県におけるツツガムシの分布,広島県衛生研究所研究報告,第38号,p17-p21.
- 岩崎 博道ら(2001):広島県において見いだされたツツガムシ病多数例の臨床的および疫学的解析,感染症学雑誌,75巻,5号,p365-p370.
- 渡辺 公登ら (1998):戸河内町国保病院における過去5年間に経験したつつが虫病15症例の検討,広島医学,51巻2号,p160-p162.
関連サイト
- 感染症の話:ツツガムシ病
(国立感染症研究所感染症情報センター) - 感染症の話:日本紅斑熱
(国立感染症研究所感染症情報センター)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

