ヤングケアラーだった私たちから伝えたいこと。
ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供をいい、責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
そんなヤングケアラーについてより具体的に知っていただくために、元ヤングケアラーの方々へのインタビューの様子を紹介します。
共感する人、励まされる人、あるいはよく分からない人。受け止め方は様々だと思います。
このインタビューは、家事や家族の世話などから生まれる様々な悩みを抱える子供だった、そんな方々のお話です。
1人目 平井 登威(ひらい とおい)さん
精神疾患の親をもつ子ども・若者の支援団体 NPO法人CoCoTELI代表
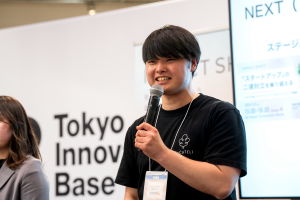
自分がヤングケアラーかもしれないと気づいたのは、同じ境遇の人と知り合った、ほんの数年前のことです。
父に通院歴があったことは知っていましたが、家族がその話をしてくれたことは一度もなく、不安定なときには暴力すら振るう父に対し、家族は24時間気を使い、萎縮しながら生活していました。
ぼくは、そんな家庭で育った子どもでした。
大好きでもある親の意を汲み、顔色をうかがう中で、自分が今何を感じているのか、どう思っているのかさえ、わからなくなっていく。
それが自分にとっての「日常」だからこそ、「誰かに相談する」こともありません。
親からも、社会からも、そして自分自身からも「見えなく」なっていく——それが、「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちです。
ぼくは、そんな子どもたちが自分らしくいられる場所——たとえるなら、「自分のためだけに息ができる場所」は、日常の中での「誰か」との関わりの中にあると思っています。
この「誰か」は、特別な資格を持った人のことではありません。
たまたま彼らと関わることになった、普通の人のことです。
「この子はいい子/悪い子」といった先入観ではなく、ただシンプルに話に耳を傾け、笑顔で声をかけてくれる人。
彼らを傷つけず、受け止め、一人の人間として「見て」くれる人。
そんな、子どもたちが安心して関われる「誰か」が一人でも多くそばにいてくれたなら——それが子どもたちの支えになり、居場所になり、やがては親御さんも含めた支援へとつながる第一歩になると信じて、今活動を行っています。
また、ヤングケアラーだった当時、ぼくは大好きだったサッカーにも支えられていました。
もし、これを読んでいるあなたがぼくと同じような経験をしていて、今はまだ誰かに話そうとは思えないのなら、まずは自分の「好き」を大切にしてあげてください。
今はまだ、そうはできない環境にいるかもしれません。
でもきっと将来、その「好き」があなたの居場所になり、あなたを支えてくれる。
最後にそう伝えておきたいと思います。
2人目 小林 鮎奈(こばやし あゆな)さん
・東京都品川区ヤングケアラーコーディネーター
・こどもぴあ副代表、一般社団法人ヤングケアラー協会事務局

母が心の病気になったのは、私が小学校2年生の頃です。
「お母さん、どうしちゃったんだろう?」と感じることが増え、それまでの日常が急速に変わっていきました。
不安定な母をみながら、子どもなりに家族のサポートを頑張ろうと食事も作るようになりました。
小学生時代は褒められると嬉しい年頃です。親戚から「あゆながお母さんみたいだね」と言われ、ますます頑張るようになった小さな私がいました。
母の病名を小学校高学年で教えてもらいましたが、それがどんなものなのかわかりませんでした。
私が頑張っても母の病気は一向に良くはなりません。「病気なんだから仕方ないんだ」と、やりきれない気持ちにも蓋をするようになりました。
「お母さんを治すためには、私がもっといろんなことを頑張ればいいんだ」いつもそう思っていました。
しかしそれが何年も続くと、さすがに疲れてしまいます。
周囲の人をみながら、「どんなに大変でも、大人は遠巻きに見ているだけ。」自分勝手で助けてもくれない大人への不信が募り自暴自棄になった中学生の私は、やがて学校にも行かなくなりました。
それは当然の感情の発露だったとは思いますが、学校の先生からすれば「問題行動」に映ったのでしょう。ずいぶん叱られもしました。
その後、私はインターネットで母の病気について情報を得たのをきっかけに、より理解を深めたいという思いから、定時制高校を経て看護学校へと進みました。
精神疾患の患者の家族が集う「家族会」という場の存在を知り、初めて訪れたのもこの頃です。
「こういう気持ちを人に話してもいいんだな」——初めての経験に安堵し、同じような子どもの立場の方と出会った時は、思わず泣いてしまったことを覚えています。
現在はヤングケアラーのための活動を行っている私ですが、もしあの頃の小さな私が、今の私に「辛い」と言えたかといえば、それは難しかったと思います。
相談をしたり言葉にできるほどのスキルは持っていませんでした。
それでも、自分のことを気にかけてくれる大人がいたら、生きることの励みになりました。
挨拶や日常の会話からでも十分です。気にかけている大人がいること、ひとりぼっちで頑張る必要はなくて、一緒に考えてくれる人もいるかもしれないと感じてもらうこと。まずは、そこからだと思っています。
