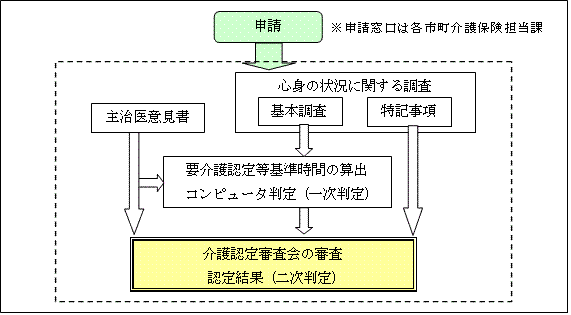要介護・要支援の認定制度について
要介護・要支援の認定制度について
1 要介護(要支援)認定とは
介護保険制度では,寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や,家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)となった場合に,介護の手間の必要度合いに応じた介護(予防)サービスを受けることができます。
この要介護状態や要支援状態にあるかどうか,要介護(要支援)状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり,全国一律の基準に基づき,保険者である市町が設置する介護認定審査会による審査判定を経て市町が判定(認定)を行うしくみです。
なお,認定の区分は,介護の手間の量(介護の必要量)により,要介護状態は5段階(要介護1~5),要支援状態は2段階(要支援1,2)に区分されています。
※ 要介護認定を受けなくでも,[基本チェックリスト]により,介護予防や生活支援が必要と判定された方は,介護予防・生活支援サービス事業を利用することができますので,お住まいの市町に相談してください。
2 要介護(要支援)認定の流れ
(1) 要介護認定の申請
介護サービスを受けようとする被保険者は,お住まいの市町の介護保険担当窓口に要介護(要支援)認定の申請を行ってください。
※ 申請方法については,お住まいの市町にお尋ねください。
※ 40歳以上65歳未満の方は,特定疾病と定められた16疾病に該当する場合にのみ要介護認定を受けられます。
(2) 認定調査の実施
申請後,認定調査員が申請者のご自宅や施設等を訪問し,定められた調査項目に沿って,申請者の心身の状態や介護の手間(介護の必要量)について調査を行います。
(3) 主治医意見書の作成
主治医が主治医意見書を作成します。
※ 市町が申請書に記載のある主治医に作成を依頼します。
※ 主治医がいない場合は,市町の指定医が診断をし,意見書を作成します。
(4) 一次判定
認定調査結果と主治医意見書をもとにコンピュータ判定を行います。
(5) 二次判定
保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により,一次判定結果,主治医意見書等をもとに介護の手間の量を総合的に審査・判定します。
(6) 要介護認定結果の通知
市町は,介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護認定を行い,申請者に結果を通知します。
認定は,原則として申請日から30日以内に行われますが,特別な事情により30日以内に結果を通知できない場合は,市町は申請者に延期の通知を行います。
(7) その他
要介護認定の有効期間が切れた後も介護(予防)サービスを受けたい場合は,更新申請をする必要があります。(有効期間満了日の60日前から受付)
また,有効期間満了前でも,心身の状態が変化し介護の手間の増減により,現在の要介護度とは違う要介護度に該当すると考えられる場合は,有効期間内であっても,[区分変更申請]をすることで,再度審査判定を受けることができます。
なお,更新申請及び区分変更申請後の流れは,(2)~(6)と同じです。
3 要介護(要支援)認定に係る調査事務の委託(指定市町村事務受託法人)について
市町は,要介護(要支援)認定に係る認定調査事務を,都道府県知事が指定した指定市町村事務受託法人に委託することができます。
※ 初めて要介護(要支援)認定の申請をした場合の認定調査は,市町又は指定市町村事務受託法人のいずれかが行います。
※ 指定市町村事務受託法人は,都道府県知事が要件を審査して指定します。
※ 指定に係る相談は,広島県医療介護保険課介護保険者支援グループへ。 (電話082-513-3207)
■ 全国の指定状況はこちら(独立行政法人福祉医療機構(Wam Net))
ダウンロード
テキスト関係
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)